古紙相場の現況につきまして
ご承知のように、ギリシャ危機に端を発した金融不安は、世界の製造業を直撃しておりますが、それと同時に各種原料相場の暴落も招いております。
リサイクルとは、一度使われた品物を新しい製品を作るための原料とすることですので、当然、世界同時の原料価格暴落に無縁ではありません。
鉄スクラップ、ペットボトルに代表される合成樹脂、電線・なべ・釜などの非鉄金属、そして古紙・・・
すべてのリサイクル原料の価格が暴落いたしております。
その事情を、弊社の主力取り扱い品目である古紙を例に、その現況についてご説明申し上げたく存じます。
国内使用量を回収量が上回る
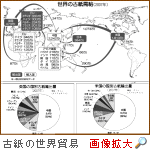 我が国の古紙回収率は、環境保護機運の盛り上がりやゴミ減量の施策、それに何よりも皆様のご協力により年々増加しておりまして、約70%に上ります。 これは古紙の回収量をトイレットペーパーやティッシュペーパーなど再生不可能な紙をも含めた国内の紙生産量で割った値ですので、かなり高い率だと考えて良いと思われます。しかしながら一方で、古紙の利用率は技術的制約があり、約60%にとどまっています。
我が国の古紙回収率は、環境保護機運の盛り上がりやゴミ減量の施策、それに何よりも皆様のご協力により年々増加しておりまして、約70%に上ります。 これは古紙の回収量をトイレットペーパーやティッシュペーパーなど再生不可能な紙をも含めた国内の紙生産量で割った値ですので、かなり高い率だと考えて良いと思われます。しかしながら一方で、古紙の利用率は技術的制約があり、約60%にとどまっています。
つまり国内では、原料として使用する量よりも回収量の方が多く、余った分は輸出することによって世界の需給バランスに寄与していました。
こうした事情は、古紙だけにとどまらず、鉄にもプラスティックにも非鉄金属にも、リサイクル原料のすべてに当てはまります。
中国需要が瞬間的に激減
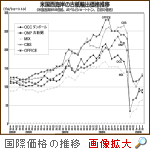 日本は中国製の製品をたくさん輸入し、その輸入品は中国で作られた段ボール箱などで梱包されて来るわけですから、製紙原料が不足している中国にそれらの段ボールを回収して古紙として輸出することは、資源リサイクルの面でも理屈にかなったことでした。
日本は中国製の製品をたくさん輸入し、その輸入品は中国で作られた段ボール箱などで梱包されて来るわけですから、製紙原料が不足している中国にそれらの段ボールを回収して古紙として輸出することは、資源リサイクルの面でも理屈にかなったことでした。
世界の工場と言われる中国ですが、都会はまだしも、地方に行きますと我が国の昭和30年代に似て、古新聞などの紙類はまだ焚付けに使うような状態で、古紙の回収は思うに任せない現状があるのです。
そうした中国はこの金融危機の影響を最も受けた国のひとつで、工業生産全体が一挙に落ち込み、紙も例外ではなく、古紙輸入量は一気に落ち込みました。また価格面でも、世界の古紙相場を引っ張ってきた中国でまず、危機勃発とほとんど同時に、古紙価格を1/4にまで下げるという状況になってしまったのです。
古紙は、生産調整が出来ない商品
しかしながら中国は発展途上の国。 現在までに発展したのは沿岸の都市部に限られ、内陸部には資金さえあれば膨大な需要があります。
外需に頼って発展してきた中国ですが、世界同時不況で輸出が冴えないとあれば世界最大の外貨準備などを利用して内陸部に資金をつぎ込み、内需重視に政策を転換することも出来たのでしょう。
ほどなく2009年の春頃には、中国の古紙需要は従前の規模にまで回復し、日本からの古紙輸入量もまた回復しました。
ところがその頃には、今度は日本国内の製紙メーカーの操業状態が不振を極めるようになっていたのです。
中国に輸出していると言っても、国内で回収される古紙の主たる需要家は国内メーカーです。
その国内での需要が収縮してしまったために、いきおい、古紙は中国向け輸出に頼らざるを得ない状況になっています。 そうして輸出圧力が高まると、一旦下がってしまった古紙の国際価格も、おいそれとは回復しないのです。
このように初めは中国の輸入激減で供給過剰に陥って価格の暴落を招いた古紙ですが、今では国内需要の不振がそれに輪をかけていて、価格の回復は遠のくばかりという状況に陥っています。
そしてそれには、古紙だけでなくリサイクル原料全般に指摘できる特徴なのですが、需給調整にある欠陥を抱えていることも指摘できます。
古紙や鉄スクラップを始めとするリサイクル原料は、いかに供給過剰だと言っても、一般の工業製品のように需給調整のための生産調整ができない商品であるというところに、問題の難しさがあります。 古紙は発生物であり生産物ではないため、「発生調整」などという手段はあり得ないのです。 一時の需要減退(紙製品の製造の減退)が、古紙発生の減少となって具現化するのには、かなりのタイムラグがあります。
しかしながら古紙発生が減少した時には、需要が旺盛な時期に差し掛かっているかも知れない・・
無駄に焼却されるゴミを増やさないためにも発生した古紙は全量回収が必要で、一朝一夕には立ち上げることが出来ない回収ルートは、何としても維持せねばならないのです。
古紙は、長期間在庫に向かない商品
しかももう一方で、古紙は長期間在庫に適さない商品です・・
集められた古紙は、需要がなければ当然古紙業者の在庫として倉庫に滞留するわけですが、ここにも難しい問題があります。
古紙はその重量・体積の割には価格が安い・・ つまり付加価値の低い商品です。
回収され、選別・プレス加工といった一連の処理を済ませた古紙は、1m×1m×2mくらいのかたまり(重量1トンくらい)になってストックされますが、都市部の場合、このように加工されたものであっても低グレード古紙をほんの1〜2ヶ月も在庫すると、販売価格を倉庫料が上回ってしまう場合すらあります。
この古紙在庫を、都市部ではなく保管料の安価な郊外の倉庫に移動させるのにも、運賃その他で、たちまち販売価格を上回る経費がかかることになってしまう・・
つまり、古紙は長期間在庫にふさわしくない商品なのです。
そのために古紙業界の在庫能力は、伝統的に低い水準にならざるを得ませんでした。 集まった古紙は、選別・プレス加工を済ませたあとは右から左へと流れるように流通しなければ、商売にならない商品なのです。
このような事情から、元々古紙業界は大きな在庫能力を持たず、保管場所が古紙選別作業などと共用の場合が多くなっています。 ところが古紙が余りはじめると、売れなくて在庫が増え、しかも毎日同じように古紙の入荷は続く・・ 作業場は在庫古紙で圧迫され、選別・プレス作業さえ困難になる・・
在庫に圧迫され物理的に操業継続すら難しくなると、いきおい、投売り状態が現出し、相場の下落に拍車をかける結果ともなります。 もちろんそこには、業者の財務的理由もあるのですが、それに輪をかけて、この在庫による操業圧迫は深刻な影響を与えているのです。
昨秋、金融危機に端を発した古紙需給の緩みと価格下落、それに在庫の増加という現象は、すでに昨年末には顕在化しておりましたが、年末の大掃除による古紙大発生期を過ぎた今年の初め、より深刻さを増しました。
年明け後の価格の下げ幅は一段と大きくなり、そしてその下落ペースも加速度的に速くなり、3〜5月頃まで続きました。
それ以後は、中国需要の復活などで小康状態を保ってはいますが、需給が緩んでいること、大きな在庫を抱えていること、そして価格が下がったままであることに変化はありません。
私どもも、経費節減と作業効率のアップなど最大限の努力を続けてまいりますが、今後の古紙価格の推移は、右に転ぶか左に転ぶか、予断を許さない状況となっております。
つきましては、現状では古紙買受価格の下落など、不本意なお願いをいたさねばならないことも多いのですが、お客様にはなにとぞ、現況の厳しさをご理解賜りたく、このような文書をしたためた次第です。
なにとぞ、よろしくご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
有限会社ヤスモトは、どのような苦しい状況になろうとも、一朝一夕には構築できないリサイクルルートの維持のためにも、力のかぎり、一層の努力を惜しみません。
|



